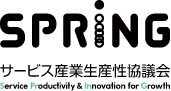コラム:【連載】CS向上を科学する
-

2025.11.28【連載】CS向上を科学する
【CS向上を科学する:第131回】(新刊)事前期待 第2部 進化を鼓舞する ― より ~事前期待の進化とマネジメント~
現在の価値を高いレベルで再現する「リ・プロデュース」(深度0)を越え、次の成長ステージへと進むことが不可欠です。
-

2025.11.07【連載】CS向上を科学する
【CS向上を科学する:第130回】(新刊)事前期待 第1部 リ・プロデュースする ― より ~属人化を打破せよ。「価値の設計図」で掴む、再現性と伸びしろ~
本書の第一部「リ・プロデュースする」では、まずはじめに、現在応えることができている事前期待の中から的を見定めます。
-
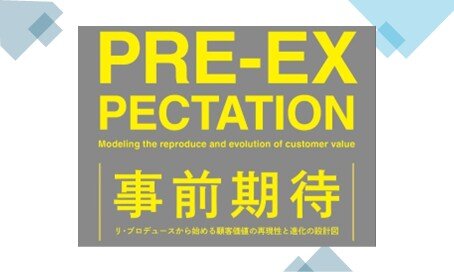
2025.10.14【連載】CS向上を科学する
【CS向上を科学する:第129回】新刊:事前期待 ~リ・プロデュースから始める顧客価値の再現性と進化の設計図~
当コラムで問いかけ続けてきたサービスとCSの本質である「事前期待」をテーマにして、一冊の書籍が完成いたしました。
-

2025.08.22【連載】CS向上を科学する
【CS向上を科学する:第128回】人材採用プロセスを事前期待でモデル化する
かつて「人材を選ぶ」立場にあった企業は、今や「人材に選ばれる」ための戦略が喫緊の課題となっています。
-

2025.06.23【連載】CS向上を科学する
【CS向上を科学する:第127回】誤解「ESとCSはどちらが先か」
前回、サービスプロフィットチェーン(以下SPC)というサービス経営モデルについて簡単に紹介しました。
-

2025.06.06【連載】CS向上を科学する
【CS向上を科学する:第126回】サービスプロフィットチェーンの誤解と課題
サービスの経営や事業マネジメントの質を高めようと努力している企業は多いことでしょう。